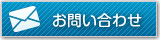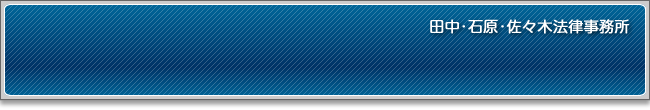
コラム|インターネット上の誹謗中傷への対処法
武蔵小杉の法律事務所、田中・石原・佐々木法律事務所の弁護士の佐々木です。
今回は、インターネット上で誹謗中傷された場合の対処法についてお話ししたいと思います。
最近のインターネットの発達により、気軽にインターネット上に自分の意見などを投稿できるようになりましたが、それに伴い、誹謗中傷など、問題のある投稿がなされることも少なくない状況になっています。
個人はもちろん、会社にとっても、誹謗中傷はイメージダウンにつながり、重大な支障を生じさせることもありますので、適切な対処法を知っておくことが重要と言えます。
1 対応法
インターネット上で誹謗中傷がなされた場合、①放置する、②削除してもらう、③投稿者を特定し、民事・刑事の対応を取るということが考えられます。
内容的にそれほど気になるものでなかったり、数も少なかったりという場合には放置という選択肢もあるかと思いますが、インターネットの特性から放置していると拡散され、被害が拡大することになる可能性も少なくないため、放置をするかは慎重に検討した方がよいと思います。
2 削除してもらう方法
(1)サイト管理者の特定
削除してもらう場合、まずは投稿がなされているサイトの管理者を特定する必要があります。
その方法には、サイト上に運営会社などと表示されている会社を確認したり「WHO IS」というサイト(ドメイン名などから業者を調査することができるサイト)を利用することが有効です。
(2)サイト管理者への要請
サイト管理者がわかれば、その管理者に対して、任意に削除してもらうよう、要請をすることができます。
この場合、管理者に対して書面やメールを送る方法もありますが、サイトによっては削除要求の手続きがサイト上設けられている場合もありますので、これを利用すればよいでしょう。
削除は比較的任意交渉で対応してもらえることもありますので、検討するとよいでしょう。
(3)裁判所の手続
任意の要請に応じてもらえない場合には、裁判所の手続をとることになります。
具体的には「削除の仮処分」と「削除請求の訴訟」があります。
通常、仮処分によって仮に削除するよう命じられれば、それをもとに削除に応じてくれますので、仮処分によって目的を達成することができます。
仮処分でも対応してもらえない場合には削除請求訴訟を提起し、削除を命じる判決を出してもらう必要があります。
3 投稿者を特定し、民事・刑事の措置を取る方法
(1)サイト管理者の特定
この場合でも、サイト管理者を特定する必要があります。その方法は上記と同様です。
(2)投稿者の特定のための手続
削除の場合と異なり、投稿者を特定するための手続は多少複雑になります。
この場合には、発信者情報開示請求という手続をとることになるのですが、上記のサイト管理者に開示請求してすぐに投稿者が特定できるとは限りません。
たとえば、2ちゃんねるなど匿名で投稿できるサイトなどの場合、接続プロバイダを経由して当該サイトに投稿されているため、サイト管理者に投稿者を開示せよと言っても、開示されるのは、どこのプロバイダを経由して投稿がなされたかということまでです。この場合には、接続プロバイダに対して改めて投稿者の情報を開示してもらうための手続をする必要があります。
現実的に誹謗中傷が問題となる多くは、匿名で投稿されている場合ですので、以下はその場合にとるべき手続の流れをお話しします。
ア サイト管理者に対する発信者情報開示仮処分
サイト管理者に対して、接続プロバイダがどこの業者であるかを開示するよう求める仮処分を申し立てます※。
※発信者情報の開示を任意に求めることも可能ですが、一般的に開示には応じない業者がほとんどですので、発信者情報の開示を求める場合には仮処分をする必要があります。
仮処分の手続では、サイト管理者の意見を聞くことになります(審尋と言い、業者は開示を争ってくることが多いです。)。
審理の結果、仮に開示する必要性があると裁判所が判断すれば、開示が命じられ、それを踏まえてサイト管理者に請求することで接続プロバイダの情報を知ることができます。
なお、この情報は業者によって異なるものの、6か月程度で消えてしまうため、投稿者を特定したいと思う場合には、早期に対応する必要があります。イ 接続プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟
接続プロバイダがわかったら、そのプロバイダに対して、投稿の際に割り当てられたIPアドレス(投稿者を特定するため接続プロバイダが割り与えている番号)を使用していた人の住所と氏名の開示を求めることになります。
これは、仮処分ではなく訴訟によって行う必要があります。
発信者情報開示請求訴訟に勝訴すれば、晴れて投稿者(が使用した接続プロバイダの契約者)の住所と氏名を特定することができることになります。
ウ 投稿者特定後の手続
その後、名誉毀損やプライバシー侵害等を理由に損害賠償請求の訴訟を提起したり、名誉棄損罪や威力業務妨害罪としての告訴などをして、投稿者に対して一定の制裁を加えることができます。
もっとも、現時点では、告訴をしたからといって捜査機関が実際に捜査などをすることはそれほど多くなく、刑事罰という制裁が投稿者に課されることは少ない印象です。
4 注意点
(1)削除を求める方法、投稿者を特定して対応する方法のいずれの場合も、その投稿が、一般読者が通常の読み方をしたときにその人に関するものだと思うものであり、さらにその人の社会的評価を低下するものであること(名誉毀損の場合)などと言えるものであることを、こちらが証明しなくてはなりません。
(2)発信者情報開示請求訴訟によって開示されるのは、投稿において用いられたIPアドレスの契約をしている人の住所等で、その人が実際に投稿をしていない場合もありますので(ネットカフェからの投稿など)、この場合には結果的に投稿者を特定することはできません。
5 最後に
以上のとおり、インターネット上で誹謗中傷などの書き込みがなされた場合、一定の手続をすることで、投稿者を確認し、対応を取ることができます。
もっとも、裁判所の手続によらなければならない等、ご本人での対応も容易ではありません。
当事務所では、このようなご相談もお受けしておりますので、インターネット上での誹謗中傷などでお悩みの方は当事務所までお気軽にご相談ください。